梅干しは自作すれば塩分調整が自由にできます。 あまり薄塩では持ちませんが、10%にすれば長持ちする梅干しを作れます。 15年後の梅干し


庭に古梅が生えています(幹に苔が付いて風情あり)。
これが毎年のように大量の実を付けます。
この梅は実は小さいですが、小さいなりに皮が薄くておいしいので、この梅で10%の梅干しを作ります。
梅拾い

地面から少し浮かせた網で受けます。
こうすれば落ち梅に虫が入りません。
地面にそのまま落としてしまうと、夜の間に虫に食われるので、必ずこのように受けてください。

斜面にはブルーシートを敷きます。
下に転がるので、斜面の方が集めやすいものです。
アク抜きと予備漬け
毎日、拾っては水を張った樽の中に付けてアク抜きをします。 自然に落ちた梅なので、軸などは残っていないので楽に作業を進めることができます。 購入する場合はなるべく完熟の梅を入手してください。 未熟な梅は軸の取り外し作業が結構面倒です。 一晩アクを抜いたら、梅の重さをメモしながら樽に入れ、塩(海塩)を少しずつ足していきます(塩の重さもメモしておいてください)。 塩は最後の梅を入れたときに10%になるようにするため、少なめに入れるようにします。赤穂の天塩 5kg
塩の調整
梅を拾い終わったら、最後に塩の量を調整します。
その年の温度や梅の熟し具合を感じながら塩分量を決めますが、慣れないウチは「塩は多めにする」方が安全です。
最低でも10%は入れないと、恐らく失敗すると思います。
※ほんの少しの量を漬けるのであれば、アルコール消毒や煮沸消毒などで塩分量を減らせます。

梅の重さ程度の重石を載せておきます。
カバーを掛けて虫などが入らないようにしてください。

透明な白梅酢が上がりました。
ここまで来ればもう完成したも同じです。
この白梅酢で紫蘇の葉を揉んで、一緒に漬け込みます。
干し開始
お盆の頃まで樽で漬けておきます。
時々様子を見て、白いカビが出ていない事を確認します。
塩が少なすぎると黴びるので、カビが少ないうちに捨ててください。また塩を足してください。
次の年からはもう少し塩を多くして漬ける方が良いでしょう。
※慣れないうちは塩は濃い方が安全です。その年の気温などで黴びやすさは変わります。

干し始めました(これは紫蘇が多いタイプ)。
晴れが三日ほど続くと良いものができます。
樽の中の梅酢にも陽を当ててください。
一日干したら、夕方には梅酢に戻します。
これを2回繰り返し、最後は梅酢に戻さずに完成です。
※落ち梅で作ると皮が非常に柔らかいので注意して扱います。

こちらは紫蘇の少ないタイプ。
赤見が少ないです。
香りも異なるので、料理によって使い分けてください。
15年経過後
梅干しを漬けて10年ほどすると、ゼリー状のペクチンが出てきます。
・ペクチンの豊富な完熟した梅を使い
・梅の重さの10%の塩を使い
・漬けた樽を冷暗所に置く
・一切手をつけない
このやり方で作った梅干しには全てペクチンのセリーができています。
このペクチンゼリーは色々な料理に使えます。
10年ほど熟成するとゼリー状のペクチンの塊が出てきます(これは15年熟成させた梅干し)。

一般的に販売されてる梅干しは、熟成期間がせいぜい一年程度です。
この梅干しは、しょっぱく、味の荒々しさがあります。
「梅干しはしょっぱい」と言われてしまうのは、この梅干しが原因です。
3年ほど熟成させると、味が滑らかになります。
3年もの程度の梅干しであればネットで入手できます。
一方、10年を越えて熟成させると、更に梅干しはまろやかになりペクチンが析出し、上品な味に変化します。
塩辛さは全く無くなり、ねっとりした柔らかな酸味だけが残ります。
このペクチンを素麺やうどんの出汁にちょっと入れたり、卓上での調味料としても使えます。
ペクチンは繊維質の塊です。ペクチンの研究情報
整腸作用や便秘解消、コレステロールや血糖値の低下作用などがあります。
折角梅干しを作るのですから、大量に作って10年20年と熟成させてみてください。
購入リンク



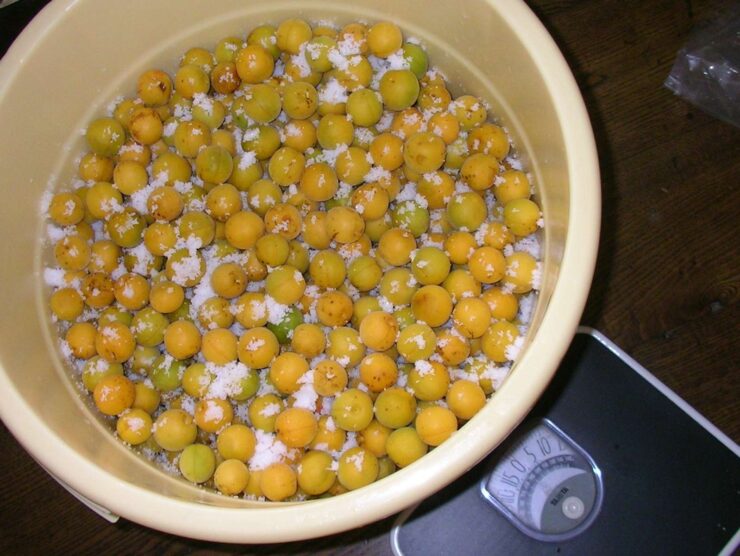


コメント